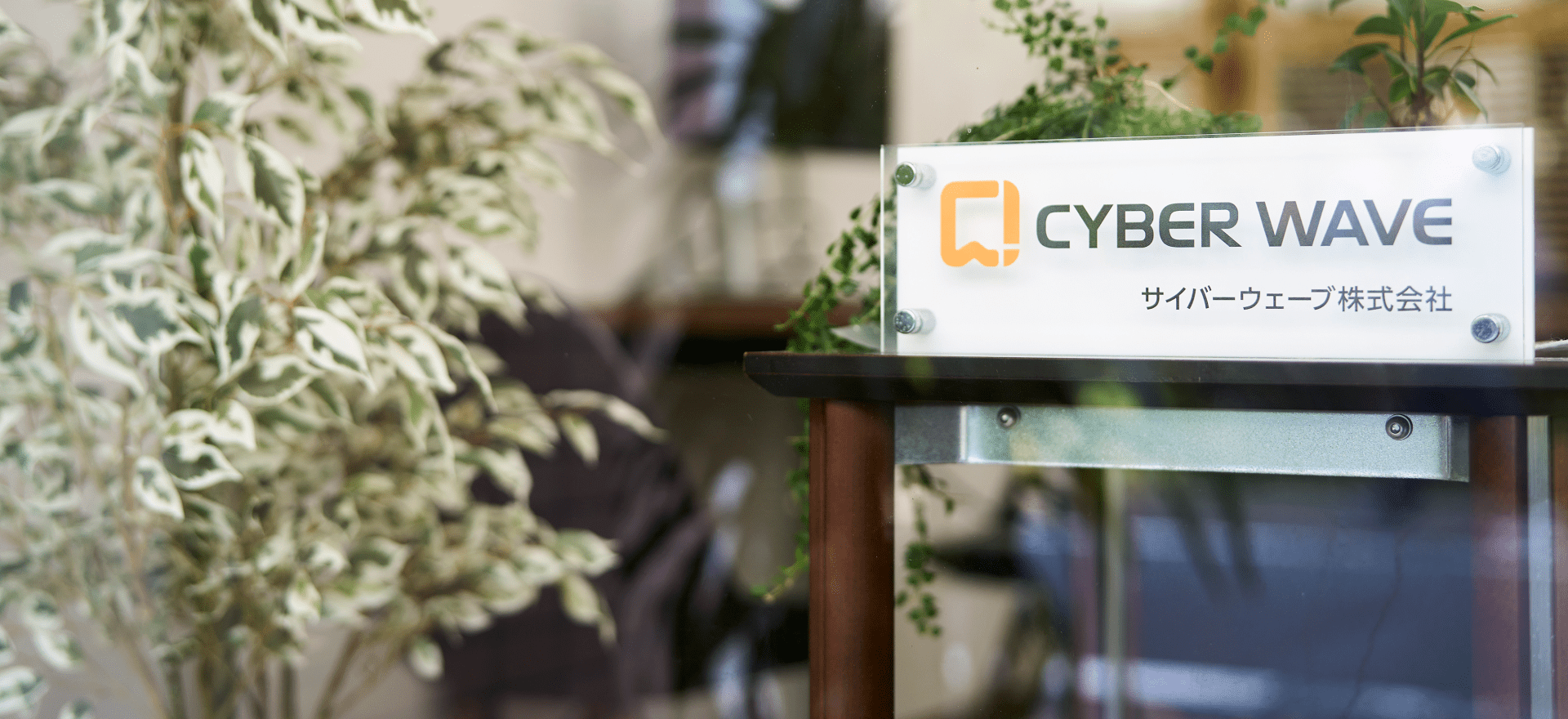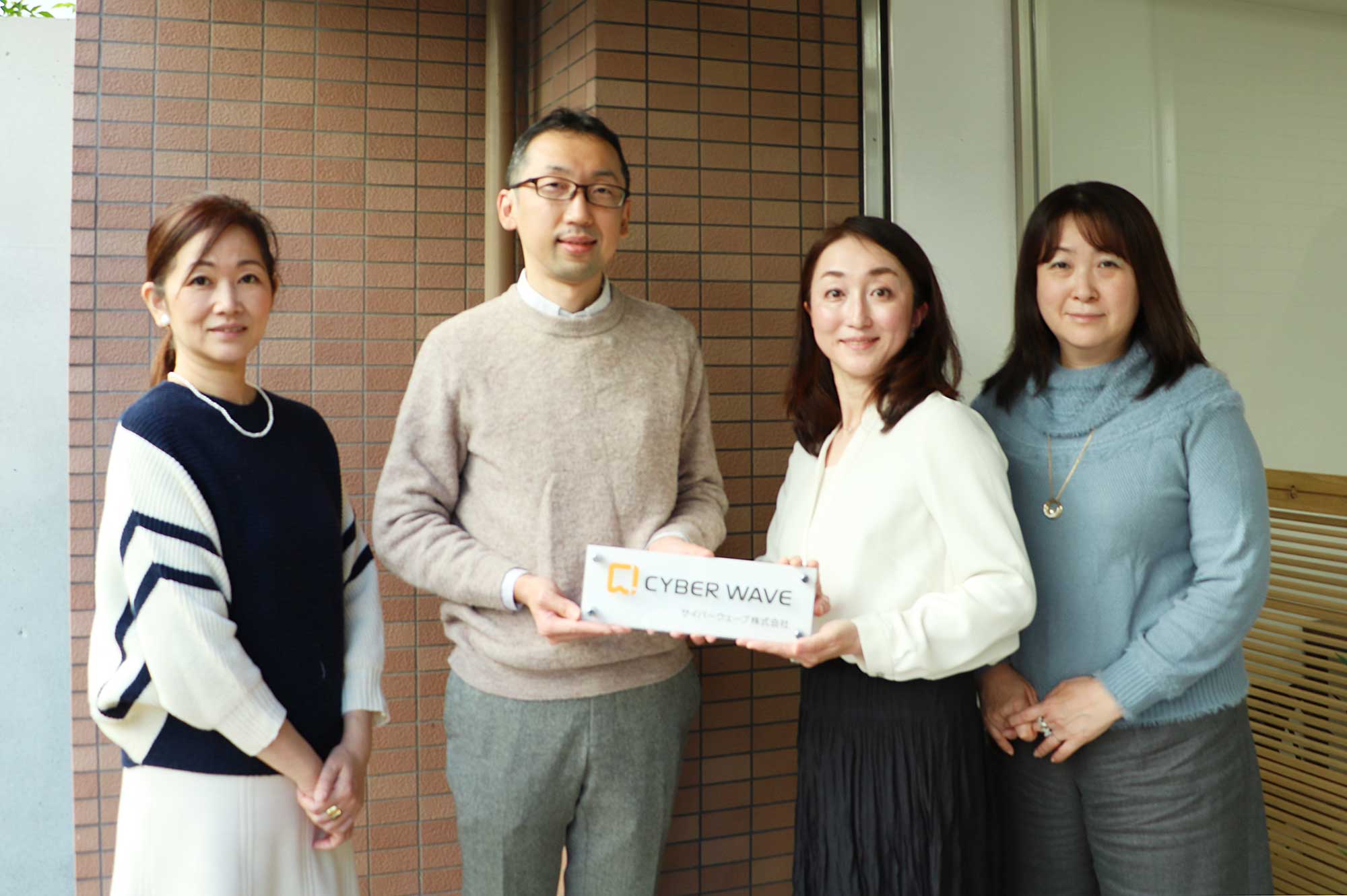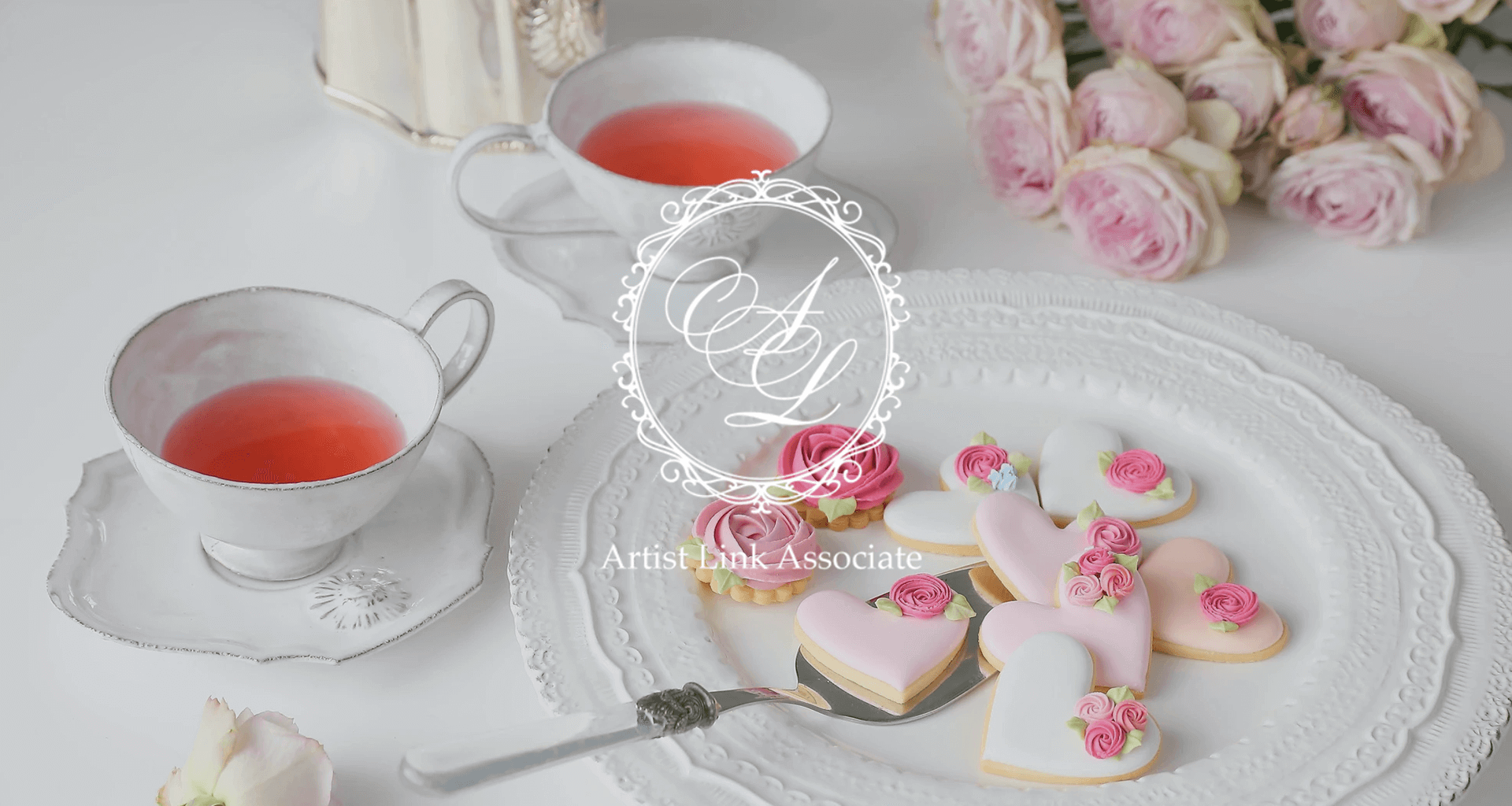01
プロダクト Product
サイバーウェーブのシステム開発は、すべて独自プロダクトのVALUE KITで行います。

発注段階で7割が完成
DXの可能性とビジネスをスケールさせる
VALUE KIT
「貴社の望みを叶える柔軟なシステム開発」 と 「短納期・費用対効果」の相反する2軸を同時に実現させる独自のシステム開発手法がVALUE KITです。
Point1
キットを組み合わせた開発で
最初から7割が完成

会員機能、決済機能などサービスを展開する際に必要な機能を25個、キットとしてご用意。このキットを使うことで貴社の手間を少なくし、組み合わせるだけでシステム開発の7割を完成させます。
Point2
貴社のご要望に応える
高いカスタマイズ性

システムの7割をキットでつくり、残り3割を自由にカスタマイズできるキット開発のため、妥協せずにこだわりを実現できます。高いカスタマイズ性で、貴社独自のシステムを完成させます。
Point3
スクラッチ開発より
短納期で費用対効果が高い

VALUE KITでは短納期で費用対効果の高いシステム開発が可能。7割をキットで効率良くつくり、残り3割でじっくりとカスタマイズ。時間とコストを最適化しながら進め、納得のいく仕上がりを目指します。
実績・事例 Case Study
大手企業が求める高い評価基準をクリアし、採用されています。
エンジニア採用情報 Recruit
WEB開発経験のあるエンジニアとプロジェクトマネジメント経験のあるリーダー職を募集しています。

自分らしく成長して、
オンリーワンのエンジニアに!
事業会社と直接、対等に話して仕事をしたい、リーダーとしてプロジェクトを推進したい、設計の仕事でスキルアップしたい、コード書きに没頭したい、いつまでも重宝されながら働きたい。サイバーウェーブではそんな目的意識のあるエンジニアを募集しています。自分らしく学び、早く成長し、誇りややりがいを感じられるような環境をご用意しています。
ブログ Blog
エンジニアブログや社内イベントをご紹介しています。
コラム Column
新規事業・既存事業のDX推進に役立つコラムです。